
「なぜ学ぶのか」
今回は“学び方を学ぶ”ことについて考えてみましょう!
「大学受験が終わったら、もうその知識は使わないのでは?」
そんな疑問を抱いたことがある高校生は少なくないでしょう。
でも、ちょっと視点を変えてみませんか?
みなさんが学校での学習を通して手にしているのは、「知識」だけではありません。
もっと大切なもの──それが学習方略です。
今回は「なぜ学ぶのか?」シリーズ第7弾として、”学習方略を手にいれる”ことについて紹介します。

人生100年時代。”学び方を学ぶ”ことは、一生物のスキルです。
高校教員として、数学を10年以上教えています。
内容をただ教え込むのではなく、「数学の学び方を教える」をモットーに授業を実施しています。
生徒が主体的かつ協働的に学ぶ授業スタイルを目指し、「なぜ数学を学ぶのか」を意識した授業を心がけています。
目次
学習方略ってなに?

学習方略って、そもそも何ですか?

学習方略とは、「学びを進めるための工夫や方法」のことを指します。
学術的には、以下のように説明されています。
学習方略は、学習の効果を高めることをめざして意図的に行う心理的操作あるいは活動。
引用:学習方略の心理学 辰野千壽(1997)
また、学習方略は「リハーサル」「精緻化」「体制化」「理解監視」「情緒的(動機づけ)」の5つのタイプに分けられます(Weinstein,C,E,et al .1986)。
高校生向けに噛み砕くと以下の表の通りです。
| カテゴリー | 内容 |
|---|---|
| 記憶したものを見ずに繰り返すこと | |
| 学習内容を覚えやすいように変換して、自身の頭の中のものと関連づけること | |
| 学習をするときに、それぞれをバラバラなものとせずに全体としてまとまりをつくるようにすること | |
| 学習者が自ら目標を立て、その達成を評価・振り返りし、必要に応じて方略を見直すこと | |
(動機づけ) | 学習環境や時間効率など学習意欲を維持するための方略のこと |
もう少し具体的に学習場面に当てはめてみましょう
上記のカテゴリーに分けなくても、みなさんが普段から取り組んでいる学習効率を高める手立てすべてが、広い意味で学習方略となります。
- 例題を読んでから自力で問題を解いてみる
- 解説を読みながら、自分のミスの原因を分析する
- 苦手な部分は複数の参考書を見て補強する
このような一連の取り組みも、学習方略と言ってよいでしょう。
学習方略は、学校の学びの中で手に入る“人生の道具”

高校での勉強とか、受験勉強って将来役に立つなかなぁって思うこともあります。

学習内容(コンテンツ)自体を仕事に活かしている人は、業界ごとで人それぞれかもしれませんね。
でも全員に共通するのが、学校での勉強を通して学び方を学んでいるのです!
高校の学びは、国語、社会、数学、理科、英語……さらに科目ごとに……と実に多岐にわたります。
そのうえ、部活動や行事、探究活動もあり、忙しい毎日を過ごしている人も多いでしょう。
そのような中で学習を進めるためには、
そして、受験が近づくと自分の状況(苦手・得意・残り時間など)を冷静に分析し、対策を講じることも求められます。
「受験勉強の内容なんて、社会に出たら役に立たない」
という声も時々耳にしますが、実はその過程で得られた“効率よく学ぶ力”は、人生においてとても大切なスキルです。
- 社会人になってからの資格試験
- 新しい仕事の習得
- 子育て・介護の知識
- お金の学習
など、いわゆる教科の学習以外にも人生には学ぶべきことがたくさんあります。
人生100年時代と言われるいま、ただ知識を身につけるだけでなく、「学び方そのもの」を獲得することがこれまで以上に大切です。
高校時代に身につけた学習方略は、受験や定期テストのためだけでなく、社会に出てからも新たな知識やスキルを自ら学び続ける力へとつながっていくのです。
どんな時代でも、学びを止めない人こそが成長を続けられる。
そのための“土台”を、高校生の今から育てていきましょう。
学習方略を獲得するには?

学生のうちに学び方を学んでおくことの大切さが分かりました。
でも勉強って苦手で…。
どうすれば身につけられるでしょうか?

あまり学術的にならず、経験談からポイントを見ていきましょう!
「勉強が苦手」という人は、学習方略が上手くないケースが多いです。
そのため正しい学習方略を獲得することで、学習効果が出やすくなるでしょう。
学習方略の獲得については、認知心理学の分野などで多くの研究が進められています。
ただ論文などは少し難しいですよね。
ここでは、私自身が学んだことや教員として多くの生徒を見てきた経験から、学習方略の見つけ方を紹介します。
効果的な学習法は、人によって異なります。
やや抽象的な話になってしまいますが、自分自身で学習方略を獲得する方法を紹介したいと思います。
① 学び方を書籍から学ぶ

まずは、正しい学習の仕方をインプットすることからです。
小学校の頃から教科の授業が始まり、テストを受け、評価されるという流れが続いてきました。
その中で、学習方略をうまく身につけた人と、そうでなかった人とで差がついてしまうのです。
本屋さんの参考書コーナーには、参考書や問題集だけでなく、「勉強法」に関する本も多く並んでいます。
それらの書籍を出している方は、少なくとも自身が学習で成功を収めている人です。
「学習法」に関する良書を読むことで、自分の勉強スタイルをアップデートすることができます。
研究者の書籍も、一般書であれば論文のような難しさもなく、わかりやすく書かれているのでおすすめです。

私のクラスに置いてある学級文庫からいくつか紹介します!
上記は書店でたまたま手に取ったものです。
みなさんも、「これは!」と思うもの、読みやすそうなもの、自分の苦手な教科に関わるものなどを探してみましょう。
▼学習を効果的にするための「学習観」については、こちらの記事も参考にどうぞ。
② 協働学習の中で学ぶ

個人でインプットすることも大切な学びですが、他者から学べることも沢山あります。
近年では、教員が一方通行で講義をする授業は少なくなってきました。
ペア学習やグループ学習を通して、他者の考えに触れながら自身の思考を深めていくためです。
そのような活動のときには、課題の解決だけでなく、周りの学習方略にも注目してみてください。
- 理解につながる解説の利用の仕方は?
- 基礎に立ちかえることで、課題解決につながった?
- 資料の集め方は?
など、問題解決のきっかけを提供できる人は、学び方が上手であることが多いです。
ただ“教える・教えてもらう”という関係性にとどまらず、思考の過程にも着目したやりとりを意識してみましょう。
また、授業外では純粋に学習の仕方を共有するのも効果的です。
友人に限らず、学校の教員などから学習のやり方を聞くことで自分の学習方略を磨いていくことができます。
その際のポイントは、一つの例だけでなく、いろいろな方法を知ることです。
誰かの学習方略は、その人が成功したやり方です。
必ずしも自分に合うとは限りません。
ある程度、効果的とされている方法はありますが、自分に合ったやり方を見つけることが何より大切です。
他人の学び方を知ることで、自分の学習方略の幅を広げてみましょう。
▼協働学習については、こちらの記事でも紹介しています。
③ 計画・実践・振り返りでメタ認知力を高める

最後は、インプットした学習方略を自分のものにするためのステップです。
「学んだことをどう活かすか」
「次はどうすればもっと良くなるか」
このように自分の学びを客観的に振り返る力(=メタ認知)は、学習の定着に不可欠です。
これは学習方略についても同様です。
中間試験に向けた学習は効果的だったか。
その反省を活かして、期末試験ではどのように取り組むか。
例えば
- ノートの取り方を変えてみる
- 学習の時間帯や1タームの学習時間を変えてみる
- 声に出す・書く・友達に説明するなど、覚え方を工夫してみる
- 問題を関連づけながら整理し、繰り返し学習する
など
日々の学習をやりっぱなしにするのではなく、
「計画を立て」→「実行し」→「振り返る」
というPDCAサイクルを繰り返すことで、学びの質は格段に高まります。
前項で紹介した
①学び方を書籍から学ぶ
②協働学習の中で学ぶ
で手に入れた学習方略が自分に合っているのか、またしっかり身につけられているのか。
最後は自分自身の試行錯誤によって、本当の意味での学習方略の獲得をしていきましょう。

最後は自分自身の経験値を積むことですね!
▼メタ認知力を高める「振り返りシート活用法」については、こちらの記事でも紹介しています。
おわりに──“学び方”は未来の自分をつくる一生物のスキル
今回の記事では、「なぜ学ぶのか」という一つの例として、「学習方略の獲得」について紹介をしました。
学習方略とは、学びを進めるための工夫や方法です。
高校での学びは、ただ大学合格のためだけにあるわけではありません。
日々の試行錯誤や、小さな成功体験、仲間との学び合いの中で、より良い学習法を身につけていくことができます。
そして、その中で得られた“自分なりの”学習方略は、一生役立つ“学びの武器”となって、みなさん未来を支えてくれるはずです。
ですから、目の前の学習に対して、「どうせ将来使わないし、意味ない」などと思わずに、自分の学び方を高めるチャンスとして捉えてみましょう。
自分に合った学習方略は、本を読んだり、友達や先生と学び合ったり、自分自身で振り返ったりしながら、少しずつ身につけていくものです。
「うまくいかないな」と感じたときこそ、自分を成長させるチャンスです。
自分らしい学び方を、焦らず育てていきましょう。

今回の記事が学びに向かうみなさんの応援になれば嬉しいです!
▼今回の記事に興味を持ってくださった方は、こちらの記事もどうぞ!

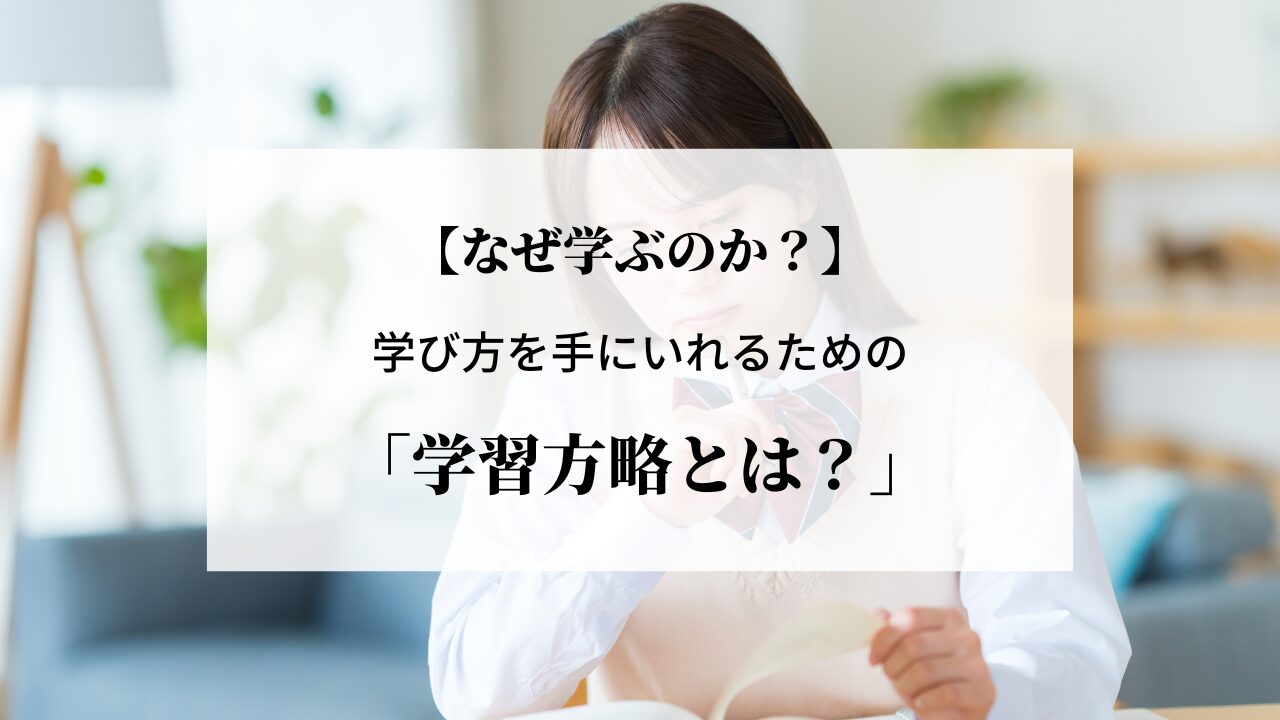
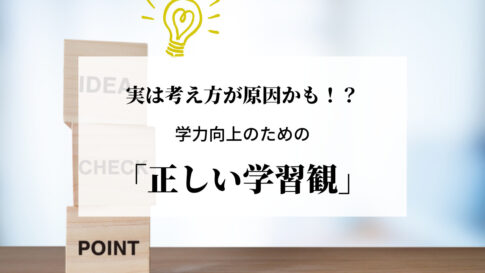
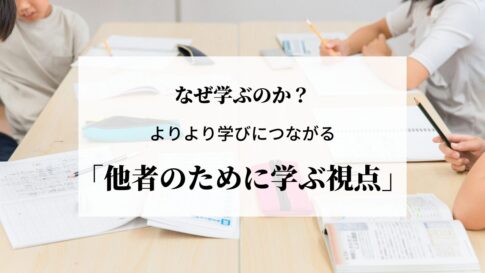
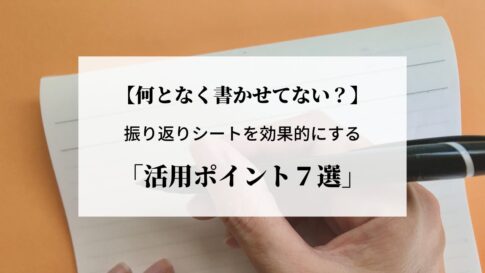
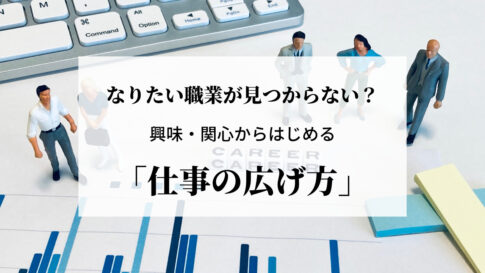
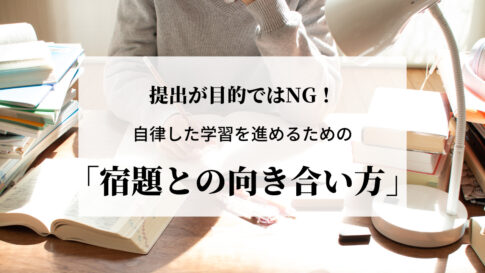
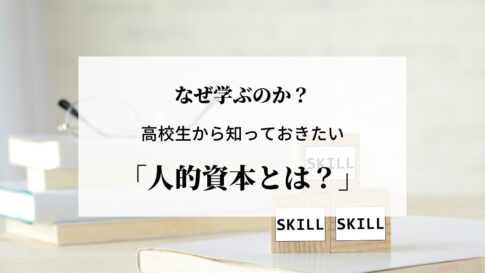
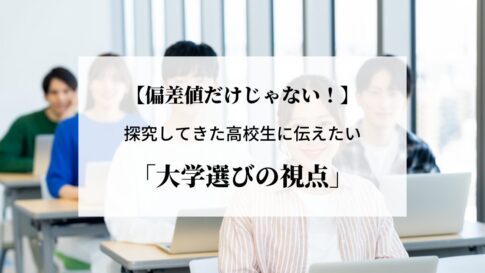
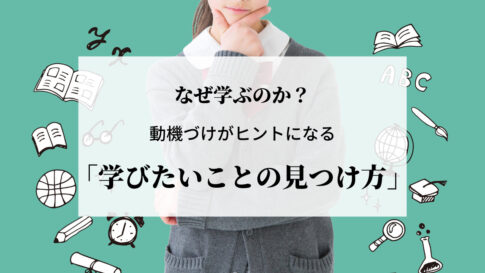
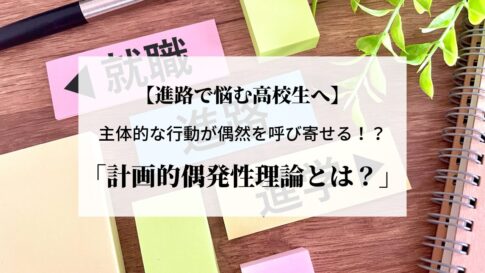
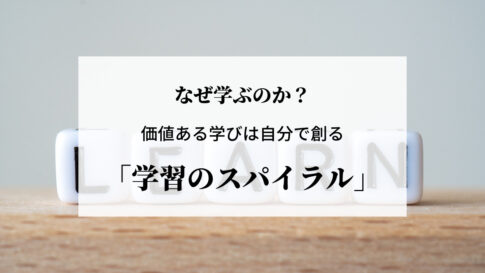
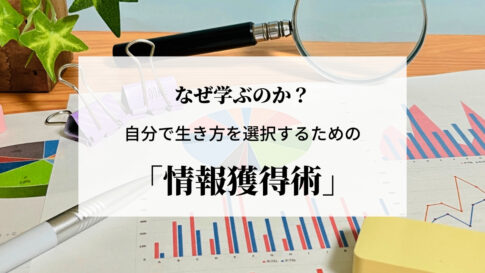










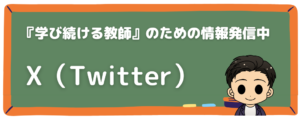
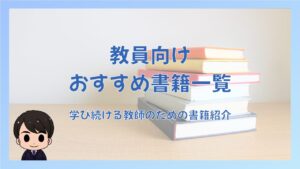
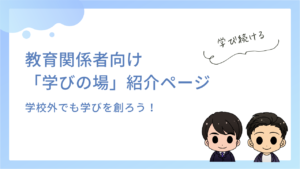
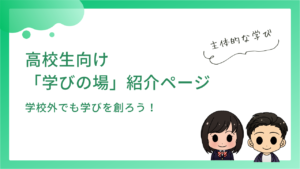
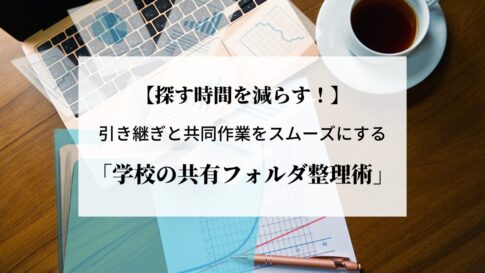
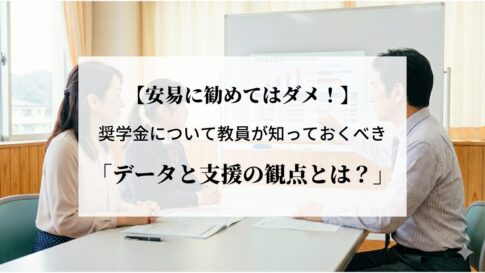
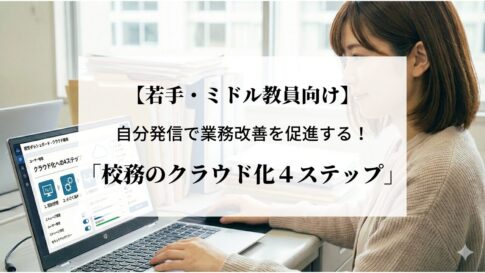
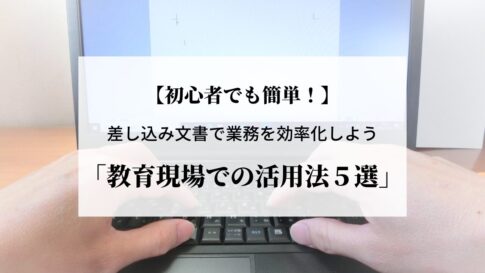
将来、数学の問題なんて使わそうなのに、なぜ学習しているのでしょう?