
二者面談などをしていても、よく聞く悩みですね。
進路について考えるとき、自信を持って希望進路を答えられる高校生は、決して多くはありません。
二者面談でも、「やりたいことが見つからない」「将来のイメージがはっきりしない」といった声をよく耳にします。
変化の激しい現代において、何十年先の進路を明確に決められないのは不思議なことではありません。
そこでヒントとなるのが、 「計画的偶発性理論」 です。
これは、キャリアを見通すのではなく、今できる行動を積み重ねていくことで、思いがけない出会いや発見である『偶然』をものにし、未来を切り開いていこうというものです。
今回の記事では、高校生が「偶然をチャンスに変えるための考え方」と、「今日から実践できる具体的な行動」について紹介します。
高校の数学教員として10年以上授業を行っています。
探究学習を中心に生徒のキャリア意識を高める実践を日々計画・実践中。
「何を学ぶのか」だけでなく「なぜ学ぶのか」を意識した授業づくりを心がけています。
目次
計画的偶発性理論とは?
学校は何かと先を見通させがち…
高校では、定期的に二者面談や三者面談を行いますよね。
面談では、以下のような質問が先生方からされます。
- 「文理選択はどちらにするの?」
- 「数Ⅲは?物理は?」
- 「気になる大学は?学部は?」
- 「将来はどんな職業に就きたいの?」
高校生になると「先を見通して選択すること」が求められる場面が増えます。
さらに、学校は何かと目標を持たせ、それらをベースに頑張らせる方法を取りがちです。
もちろん目標を持つことは良いことですが、そもそも目標を立てること自体が難しいですよね。
しかも、18年しか生きていない高校生が、将来のすべてを見通すことは難しいでしょう。
現段階で明確な進路や目標がない高校生に伝えたいことは、「今はまだ決まっていなくてもいい」ということ。
代わりに、「今できる行動に全力で取り組んでみること」。
これが、将来を見つける一番の近道なんです。
そこでヒントになるのが、今回紹介する「計画的偶発性理論」です。
計画的偶発性理論とは?

計画的偶発性理論??

簡単に言うと、「予期せぬ出来事を学びと成長の機会に変える」「その偶然を積極的に探索し、チャンスを作る行動を取ろう」ということです。
計画的偶発性理論は、John D. Krumboltz(1996)のキャリア学習理論(Learning Theory of Career Counseling)を発展させたもので、「予期せぬ出来事を学びと成長の機会に変えることができる」という考え方です。
主要な技術進歩により、近年の仕事の世界は大きく変化しています。
変化の激しい社会において、2年後、5年後、あるいは20年後の計画を正確に実現することは難しくなっています。
ですから、「いま目の前にある偶然をしっかり掴んでいくこと」「それらを成長や学びの機会としていくこと」が見通しの持てない将来に向けて、自身のキャリアを開く道筋になっていくのです。
しかし、単に「運任せ」で受動的に良いことが起こるのを待っていてはいけません。
偶然の機会を自ら生み出し、それを受け入れるための計画を立てる必要があるのです。
そのためには、行動を起こすことが鍵です。
探索的な活動に積極的に参加することで、予期せぬキャリアの機会を発見する可能性が高まります。
計画的偶発性理論の5つのポイント
クランボルツは、この偶然性を計画的に起こすために以下の5つを紹介しています。
高校生活の場面で言えば
- 興味を持ったことや、まだ知らない分野があれば、「なぜ?」「どうなっているの?」と探究する機会を積極的に探す。
- 学習や探究活動の中で、最初はうまくいかなくても、すぐに諦めずに努力を続けてみる。
- あらかじめ立てた計画に固執せず、予期せぬ出来事や新しい情報に応じて、自分の考えや行動、目標を柔軟に変えてみる。
- 「どうせ無理だ」と考えるのではなく、「自分にもできるかもしれない」「学校が与えてくれた機会を活かそう」と前向きに捉えてみる。
- 結果がどうなるか分からない状況でも、チャンスを掴むために一歩踏み出してみる。
などが考えられます。

確かに良い方向に進みそうです!でも、それが難しいんです。
具体的にどんなことをしていけばよいですか?
今すぐできる行動5選

ここからは、高校生ができる具体的なアクションを5つ紹介しますね!
① 学校の外に出てみる
授業と部活動だけで毎日が終わっていませんか?
もちろん立派な活動ですが、学校の枠の中だけという視点で言えば、「偶然」を増やすには限度があります。
部活動も他校の生徒や大学生、監督、地域の方などと関わる機会があれば、それは立派な偶然です。
ですが、自身のキャリアと直結するくらい部活動に打ち込んでいないと、その出会いを活かすことは難しいかもしれません。
学校からの課題、休日の部活動など毎日が忙しいですが、自分の興味・関心に基づいて色々な場所に訪れてみましょう。
上記のように、学校外に出てみることで新しい気付きがたくさんあります。
とりわけ学校は、「なにを学ぶのか」が中心で「なぜ学ぶのか」の視点を教えてくれることは少ないのです。
たとえば、理工学部に行くために、学ばなけれならない数学Ⅲ、物理は教えてくれるけど、理工学部に行きたいと思える授業は少ないですよね。

「なんか面白そう!」の偶然は自分で見つけないといけませんね!
② 探究活動で人に会いにいく
こちらもおすすめの行動です。
探究活動は自分の興味・関心に基づき、社会と関わりながら「問い」を深めていく活動です。
多くの高校生が調べ学習で終わってしまう探究学習。
ぜひ、学校の外から抜け出し、新しい発見を得てみましょう。
探究のテーマを進める中で、ネットだけで調べるのではなく、実際に人に会って話を聞くことは貴重な経験です。
- 最前線で課題解決をしている企業
- 最新の知見を持っている大学や研究機関
- 地域課題を解決しているNPO法人や団体 など
勇気を出してアポイントメント取ってみると、思っている以上に快く応じてくれます。
その一歩が、自ら偶然を創り出し、みなさんの将来を変えるかもしれません。

断られることも多いでしょうが、高校生ができる「リスクをとって挑戦していく活動」ですね。
相手方も時間をかけて対応してくださいます。
丁寧な対応はもちろん、事前に活動を調査したり、書籍や論文を読み込んだりするなど、インプットは欠かさないようにしましょう!
③ コンテストや発表会に挑戦する
探究活動を進めたら、コンテストや研究発表会などに挑戦してみましょう。
校内発表を行っている学校はほとんどでしょうが、外部の方からフィードバックをもらえることは、貴重な体験です。
他校の高校生や大学の先生、社会人からコメントをもらえることは、新しい発見とともに人脈形成のチャンスです。
名刺交換などで、新しい出会いがどんどん増えていきます。
不用意に1対1で大人に会わないなどの危機管理に気をつけながらも、積極的に偶然を創り出していきましょう!

意欲的な人との出会いは、自分のモチベーションも高めてくれますね!
④ 学校で紹介されるセミナー・イベントに参加する
近年、高大接続や地域人材育成の視点から、大学や企業が主催する高校生向けのセミナーや体験プログラムも増えています。
そのような案内は、学校を通して教室掲示やGoogle Classroom・Microsoft Teamsなどの電子配信などで案内が出されますよね。
気になる案内があった場合には、積極的に参加してみましょう。
「なんとなく参加してみた」イベントが、思いがけない進路のヒントになることもあります。
ただ、学校からは、新しい案内が毎日どんどん流れてきます。
後でと思っていると、興味・関心が薄れたり、申込み期限が過ぎていたりすることもあります。
「ピン」ときたら、ぜひ参加してみましょう。
また、学校への案内は、管理職(校長・教頭)を通して、関係しそうな先生のもと(進路指導主事、探究係、学年主任など)に届きます。
学校への案内は膨大ですがら、そこで教員ブロックによって「紹介しない」、多忙のため「紹介し忘れ」が起こります。
ですから、インターネットやSNSなどを通して、ここでも自ら偶然を掴みに行くことをおすすめします。

相手が用意してくれているプログラムなので、参加しやすそうですね!
⑤ 地域の活動やインターンシップに参加する
最後は、実際に現場に出てみる視点です。
地域のボランティア、商店街のイベント、行政のワークショップなども、立派な「学びの場」です。
異なる世代と関わることで、自分の価値観が広がります。
また、文部科学省は普通科の高校生インターンシップを推進しています。
希望者向けに案内を出している学校も多いので、ぜひ挑戦してみてください。
「関心のある職業」を知ることはもちろん、「今まで考えたことがなかった職業を知る」ことも立派な成長です。
探究活動を活用したり、個人で参加できるものは顔を出してみたりと、実際に活動をすることで、新しい発見や人との出会いをつくることができるでしょう。

学校の外に出るだけでなく、外の世界の一部に入っていくことも大切なのですね!
まとめ:主体的に行動し、偶然をたくさん創ることが進路決定につながる
今回は、John D. Krumboltzの計画的偶発性理論をもとに、高校生のキャリア形成について紹介しました。
計画的偶発性理論とは、「予期せぬ出来事を学びと成長の機会に変えることができる」という考え方です。
学校には、まだまだ昔ながらの考え方が根付いています。
- よい大学→よい就職
- では、将来何をしたいのか、どの学部に行きたいのか、文理選択はどうするのか
しかし、変化の激しい現代社会では、10年先ですら見通しを持ちにくく、進路決定に悩む高校生も多いでしょう。
そこで、計画的に行動し、キャリア形成のきっかけとなる偶然をたくさん見つけていく。
いまを主体的に過ごしていくことが大切です。
そのためにポイントは以下のとおりです。
これらの要素を踏まえた、高校生が学校生活の延長としてチャレンジできる行動が次の5つです。
クラスを見渡すと、なんとなく周りの友人が目標を持って進学先や就職先を決めているように見えるでしょう。
でも担任として相談に乗っていると、明確な進路目標をもっている高校生の方が少ないのが印象です。
そのため、現在進学に悩んでいる人は、あまり心配する必要はありません。
しかし、受け身では「よい偶然」は訪れないものです。
主体的に行動している高校生ほど、やりたいことが変わりながらも「自分らしさ」を大切にしながら進路決定をしています。
ぜひ、好奇心を持ちながら何事にも前向きに取り組み、自ら挑戦をしてみてください。

今回の記事が進路に悩む高校生の参考になれば嬉しいです。
▼今回の記事に興味を持ってくださった方は、こちらの記事もどうぞ!


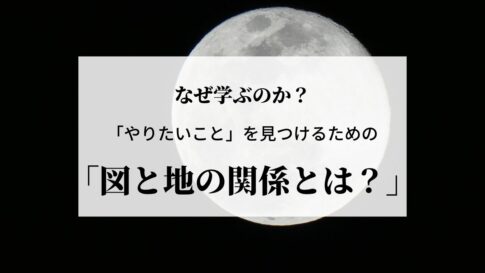
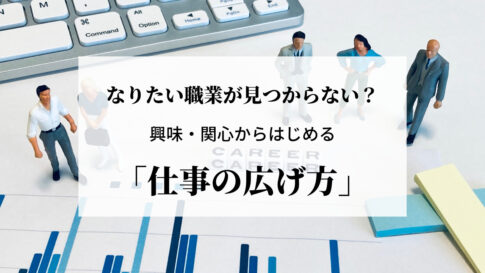
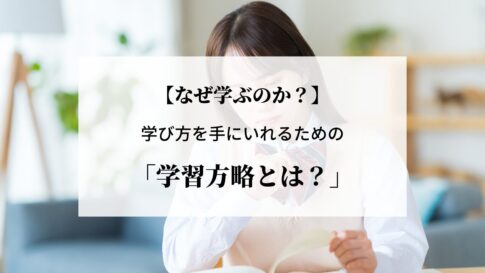
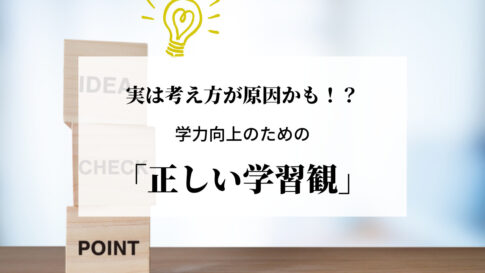
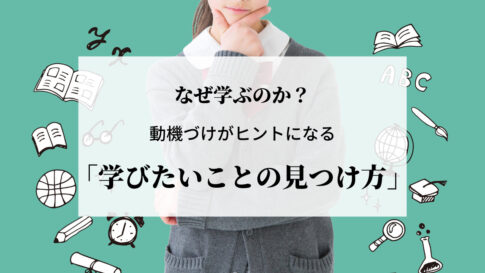
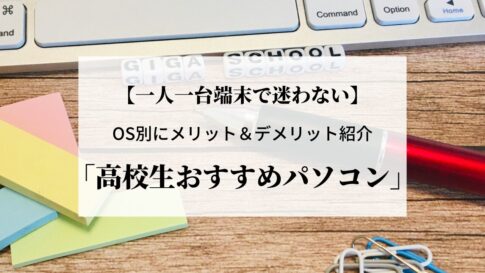
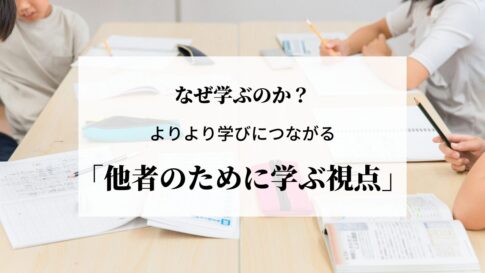
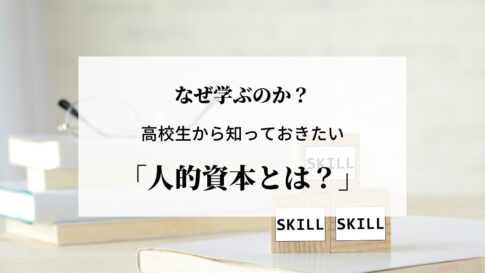
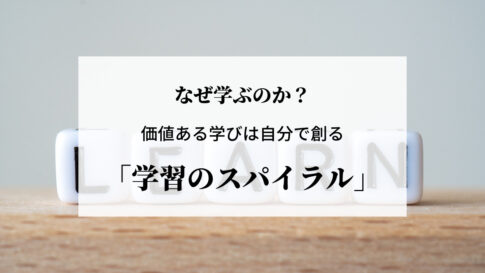
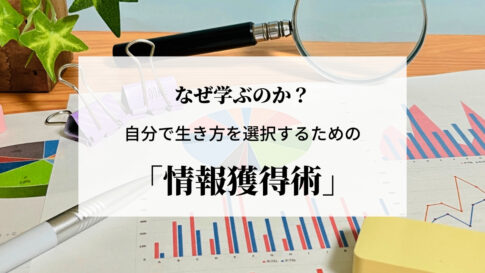










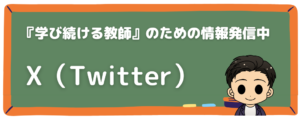
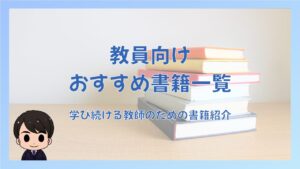
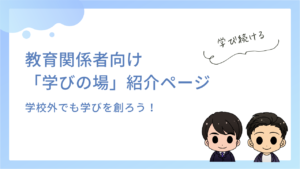
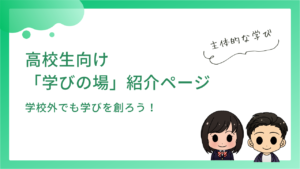
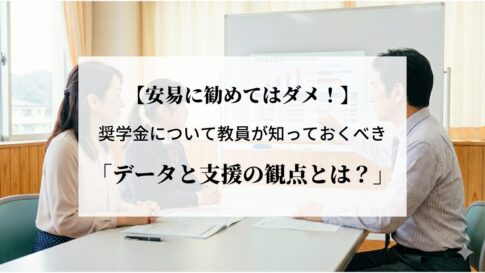
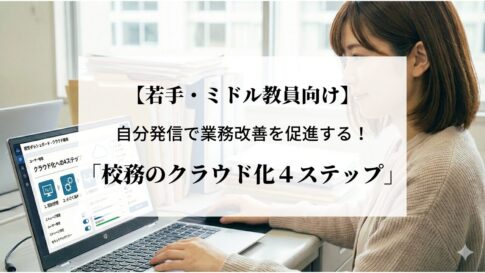
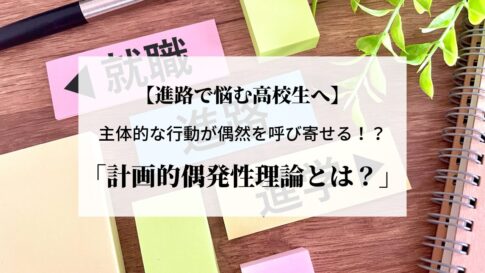
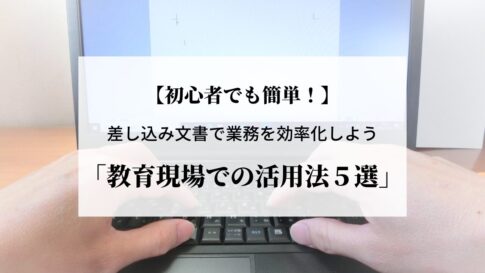
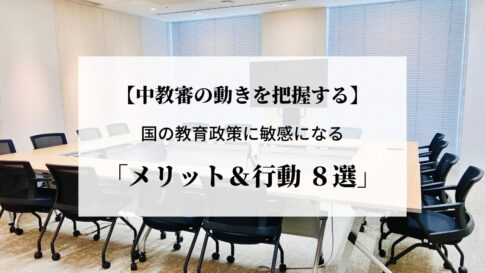
進路について「これ!」っていうのが、なかなか決まらなくて…。