
普段忙しくてなかなか中教審の動きを把握できていない先生も多いです。
しかし、国の政策をしっかり見ておくことはメリットも多いですよ!
「また新しい指導が始まるのか…」
新学習指導要領が施行されると職員室でよく耳にする言葉です。
教育の現場では、国の方針が突然降ってくるように感じることがあります。
しかし、その動きには明確なプロセスと背景があり、予兆があるのです。
同じ行うならポジティブな気持ちで、もし批判的な部分があれば建設的に考えることで、自身の教育活動を進めたいですよね。
そこで、今回の記事では、「中教審(中央教育審議会)」の動きを早期に把握することで、教員がどのようなメリットを得られるのか、また今日から実践できる行動を紹介していきます。
高校教員として、数学を10年以上教えています。
内容をただ教え込むのではなく、「数学の学び方を教える」をモットーに授業を実施しています。
毎年目標を決めて授業改善・教育活動にあたることで、教師としての資質・能力の向上を目指しています。
目次
中教審とは?

そもそも中教審って何をしているところですか?
中教審とは、「中央教育審議会」のことで、文部科学省が教育政策を決定するうえで設けている審議会です。
中教審の委員には、教育学の研究者や経済界・自治体関係者などが加わり、日本の教育の方向性を中長期的に考えています。
また、文部科学大臣の諮問に基づいて調査・審議し、文部科学大臣に報告・意見という形で答申を行います。
ですから、中教審の動きを見ることは、その時々の政府の意向や今後の教育政策を把握する上で大変重要になってくるのです。
▼中教審の詳細について、文科省HPをご覧ください。
中教審の動きを把握すべき5つの理由

学習指導要領なども最終的には現場に降りてきますよね?
教員個人が国の政策に直接アンテナを張っておくメリットって何でしょうか?

たくさんありますが、分かりやすい5つを紹介しますね!
次期の教育の方向性を早く知ることができる
中教審の答申内容は、数年後の教育施策として制度化されることが多く、「次に何が来るか」のヒントになります。
方向性を早くキャッチすることで、授業や校内の仕組みづくりを早期に進めることができます。
ここを怠ると…
「また何か変なのが降りてきた」
「あれもこれも一度に無理」
という愚痴が職員室で蔓延してしまうのです。
近年では、
- 主体的・対話的で深い学び
- GIGAスクール構想
- 個別最適な学び
- STEAM教育
- 探究的な学び
- 指導と評価の一体化
- カリキュラム・マネジメント
- ウェルビーイング(Well-being)
など、この数年でも挙げればキリがありません。
変化の激しい現代において、能動的に情報を取ってこなければ、「次々と新しい何かよくわからないものが降り注ぐ」という状態になりかねないのです。
先取りした教育活動ができる

次はポジティブに考えてみましょう!
新しい教育政策が実施されるまでには、文科省→都道府県→市町村と段階を踏むことになります。
- 都道府県の指導主事が文科省に出張をして学び、研修で現場に降ろす。
- 文科省からの通知が都道府県に降りて、現場に届く。
といった具合です。
そこで教員個人がアンテナを高く張り、自ら学びを深めておけばこのタイムラグを飛ばすことができるのです。
事前にこれからの教育の動向を把握し、義務化される前に自発的な取り組みができるので、「やらされ感」ではなく、自校の課題と照らし合わせた主体的な実践が可能です。

例えば、総合的な探究の時間を例に取ってみましょう。
高校現場で、「総合的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に変わったのは、平成30年(2018年)告示の学習指導要領からです。
こちらの全面実施は令和4年度(2022年)からでした。
その中でも総合的な探究の時間は、移行措置として令和元年度(2019)に先行実施されています。
そのような状況下で、総合の時間のカリキュラムが組めておらず、自習の時間や取り敢えずの進路学習となっている学校もありました。
そのまま全面実施を迎えてしまったことで、頭を悩ませた学校は少なくありません。
しかし、先行実施で本腰を入れて教育活動を見直した学校では、現在、探究学習推進の流れに乗って地に足のついた教育活動を行なっているでしょう。
さらに、指導要領が告示される何年も前から探究学習に力を入れている学校もありました。
結果、そのような学校は、現在の総合型選抜において、進学実績も上げています。

「先行者利益」ではないですが、未来の教育の動向をしっかり掴んで教育を進めることは、生徒のためにもなりそうですね。
政策の意図や背景がわかる

人がやる気をなくすのは、「やらされている感」ですよね。
そこへのアプローチも見てみましょう。
何度か話題にしてきた「やらされ感」。
人は、自分が納得していないもの、知らないことには攻撃的になりがちです。
さらに横文字で言われたときには、反発も多いでしょう。
そこで
- なぜその政策が出されたのか
- どんな問題意識を背景にもっているのか
がわかることで、新しい教育内容にも誠実に向き合うことができます。
これは、国の政策を全て納得して行うということではありません。
長年培ってきた、生徒の成長につながる授業方法や教育活動もあるでしょう。
- 新しい方向性は意識しつつも、自分が大切にしていることはその時々の政策に流されない。
- 文句ではなく、建設的な意見として学校運営に関わっていく
そのためにも、新しい教育政策の背景を自分自身で学んでおく必要があるのです。

校長からの伝達、たまにある研修で指導主事から言われた、などの表面的な理解ではなく、自分自身で資料を読み解き、咀嚼することが大切です。
学校運営に活かせる
現在は少子化であることもあり、高校ではそれぞれの特色を打ち出し、中学生に魅力を伝える必要が出てきました。
また、情報社会である現在、保護者も生徒も様々な教育情報にアクセスできるため、義務教育でもしっかりと学校経営方針を掲げる必要があります。
いい加減な教育をしていては、保護者や地域から連携をしてもらえません。
- 「教育の質」向上に向けて、国や自治体の方針を踏まえた取り組みを行っていること。
- 加えて、上から降りてきたからではなく、職員一人一人が方針を意識をした学校運営がなされていること。
これらが保護者や地域への信頼や安心につながります。
ただ学校は民間と異なり、圧倒的に変化が遅い文化があります。
伝統を守るというよさもありつつ、時代に置いていかれるという面もあります。
そのためにも、国や自治体の方針を早い段階でキャッチし、少しずつ学校運営に加えていく必要があるのです。
生徒・保護者への説明責任を果たしやすくなる

最後は、自分の教育活動に自信を持つことです。
「なぜこのような指導方針なのですか?」
「なぜこのような授業をするのですか?」
と保護者や生徒に問われたとき、自分の考えだけでなく、国や自治体の方針に基づく説明ができることは、信頼形成につながります。
個人の思想ではなく、国の動きとしての根拠があるからこそ、指導に説得力が生まれ、保護者の不安もやわらぎます。
また、自信を持って取り組むからこそ、結果その教育活動が上手くいくこともあるでしょう。

例えば、授業スタイルで考えてみましょう。
「主体的・対話的で深い学び」という言葉が出る前、アクティブ・ラーニングという言葉が使われていました。
やはり、教員同士でも「教師による知識詰め込み型の受験指導」と「生徒主体の能動的な学習」は対立関係にありました。
私自身の経験からも、当時は生徒も慣れておらず、「もっと解説してほしい」「先生が教えてほしい」などの意見も見られました。
しかし、丁寧に意義を伝えることで、生徒の学力・進学実績は過年度よりも高くなりました。
また、インターネットを見ていると、『「主体的・対話的で深い学び」が結局おしゃべりで終わって、結果学力が下がった』などの投稿も目にします。
これは、
という悪循環から生まれている気もします。
結果だけを見て、「やはり知識を詰め込まないと」となるのは、焦燥です。
そのためにも、まずは国の政策をしっかり学んでいく必要があるのです。
教員にできる!中教審の動きのキャッチする方法3選

中教審の動向をチェックしておく理由がよくわかりました。
実際にはどのように調べていけば良いのでしょうか?

ここからは、教員個人が手軽に国の政策へアクセスしていく方法を3つ紹介しますね!
答申を読む(要約でもOK)

まずは、本丸の「答申を読む」ことです。
中教審の存在目的の一つは、文部科学大臣の諮問に対する答申を行うことです。
この答申は、これからの教育の方向性を決める貴重な資料です。
中教審の答申は文科省のサイトに公開されています。
答申の本資料は、100ページ以上にわたるものもあり、かなりの労力を要します。
時間をあまりかけられない場合は、「要旨」や「概要」で図解などを見ながら全体像を掴み、要約された文章を読むのもよいでしょう。
ある程度新しいキーワードや方向性が分かれば、本文を Notebook LM などの生成AIに読み込ませて、チャットで質問をしながら理解を深めるのも効率的です。
詳細をしっかり押さえたい場合は、本文をじっくり読むことがもちろんベストです。
答申は定期的に出されていますが、自身の校種に関係のないものは優先して読む必要はありません。

今後の自分に影響を与えそうなタイトルは、チェックが必要ですね!
▼答申は文科省のHPからダウンロードできます。
▼ Notebook LMを使った資料のチェック方法はこちらの記事でも紹介しています。
委員の書籍を読もう

次は、より実践に近い学びを得る方法です。
中教審の委員のなかには、もちろん教育学者や現場実践豊富な教員出身者も含まれています。
それらの方々の著書では、審議に反映されるであろう考え方が丁寧に解説されています。
書籍を読むことで、中教審の議論の土台になっている教育観や課題意識を自分の授業づくりや教育活動に活かすことができるのです。
▼中教審委員の書籍については、おすすめ書籍ページでも紹介しています。
▼中教審の委員一覧は、文科省のHPで確認できます。
教育系ニュースで要点を押さえよう

なかなか時間が取れず、「政策の動きだけはキャッチしたい」という方は、教育ニュースをチェックしましょう。
中教審は答申をまとめるまでに、複数回の会議を実施します。
その結果は、報告書や議事録として公開されます。
しかし、それら一つひとつを追いかけることは難しいでしょう。
教育専門メディアでは、答申の発表はもちろんのこと、会議の報告書などについても要点を押さえた形で紹介されることが多いです。
私自身は、「教育新聞」や「月刊高校教育」を購読しており、中教審のワーキンググループの動きなどを把握しています。
▼最新の教育情報にアクセスする方法はこちらの記事でも紹介しています。
まとめ:教育情報は「待つ」から「自ら掴む」へ
今回は、中教審から出される情報を把握し、国の政策に敏感になるメリットとその方法について紹介をしてきました。
教育政策は、突然決まるものではなく、議論と検討を重ねてある程度時間をかけて進んでいきます。
その動きを早く知っておくことで、現場の教育活動をより意味のあるものにする準備が行えます。
新しい教育政策が上から降りてくるまで待つ「受け身の姿勢」ではなく、自ら掴み取る「能動的な姿勢」にすることで、もっと教育は面白くなります。
「また新しいことが始まった」
ではなく、
「この動きはここから来てる。なら、こう活かせる」
そう言える教員が増えれば、教育はもっと良くなるはずです。
中教審の動きの把握の仕方として以下の3つを紹介しました。
目の前の業務で忙しい毎日ですが、ご自身に合うスタイルで先取りの一歩をぜひ踏み出してみてください。

今回の記事が、先生方の前向きな教育活動づくりに繋がれば嬉しいです。
▼今回の記事に興味を持ってくださった方は、こちらの記事もどうぞ!

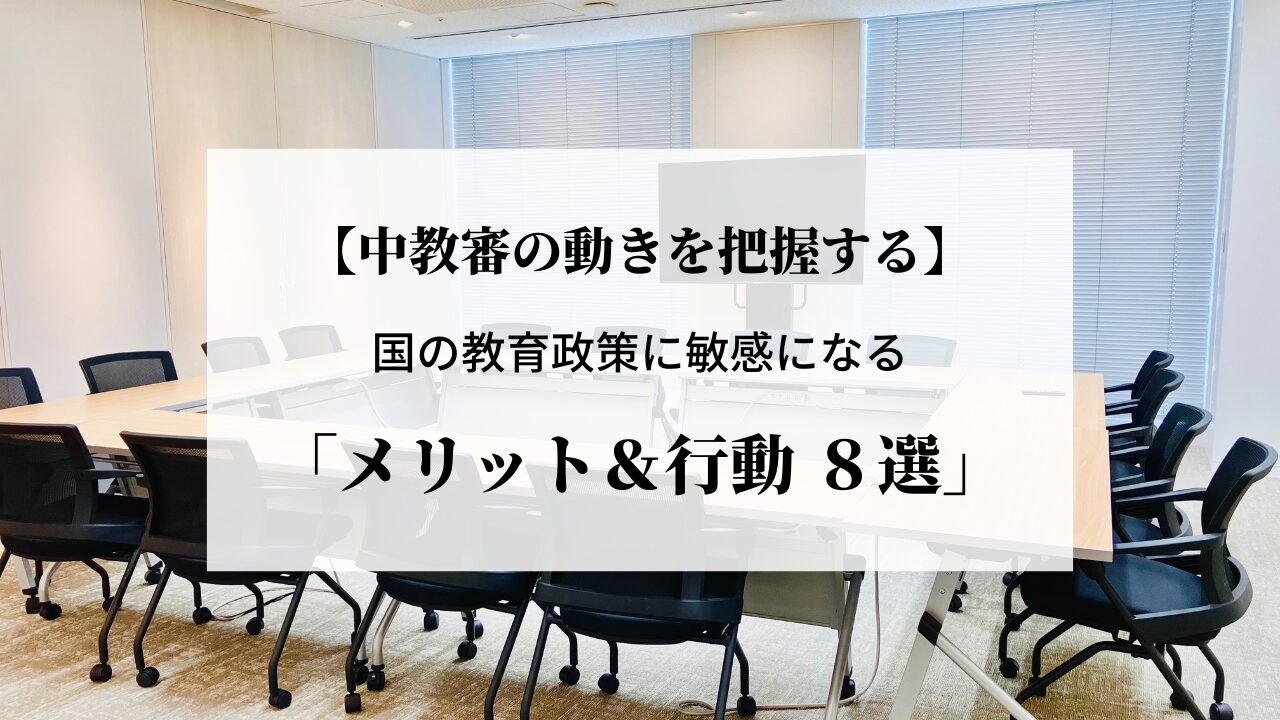

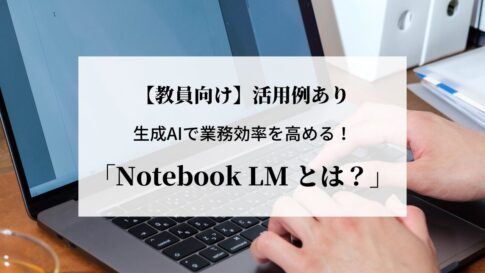
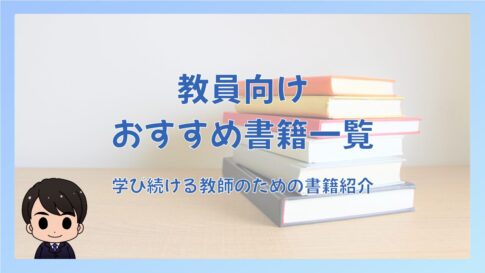
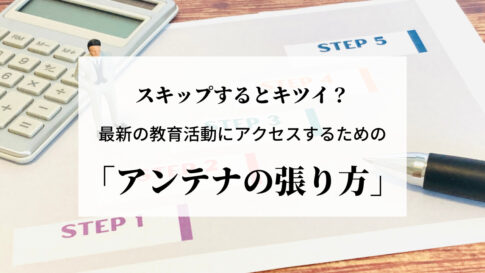
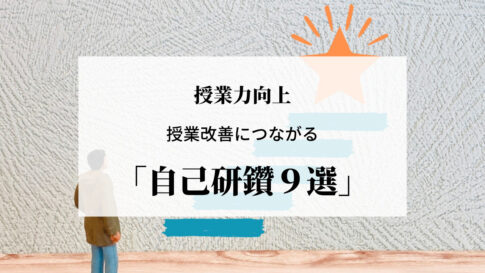
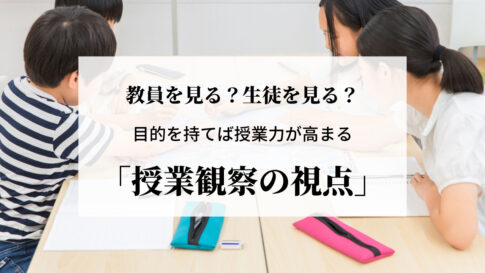
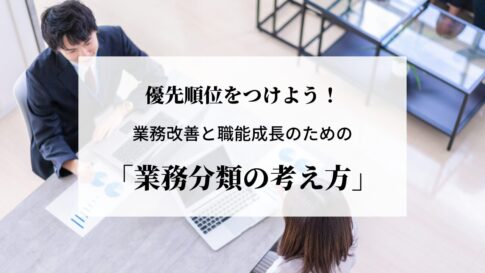
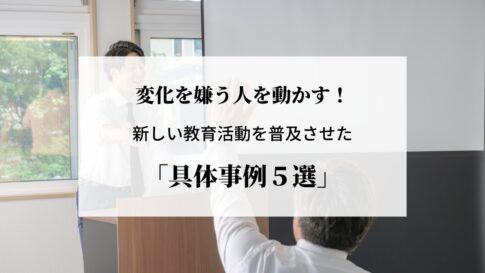
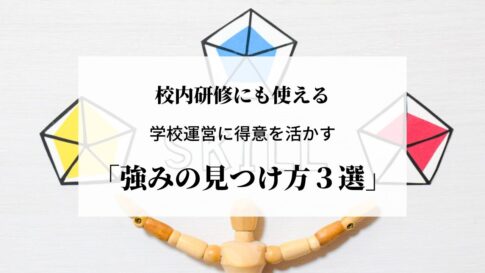
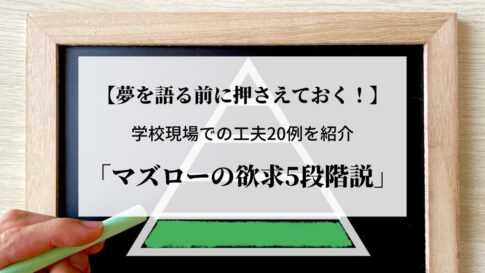
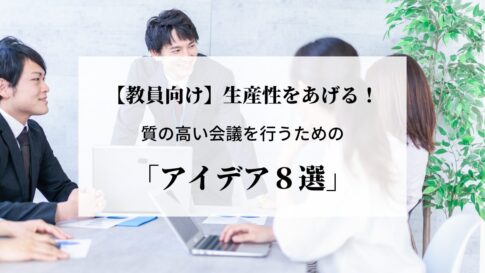
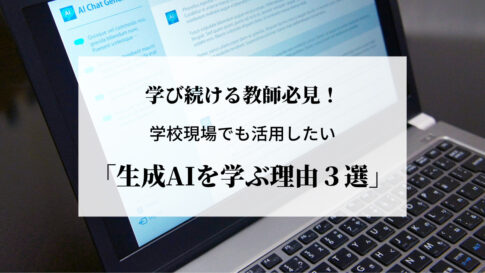
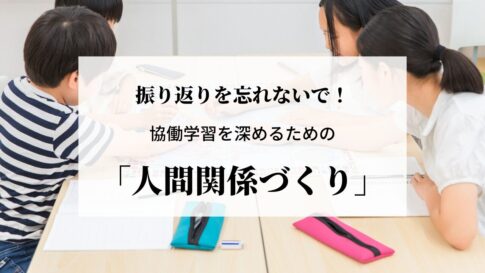
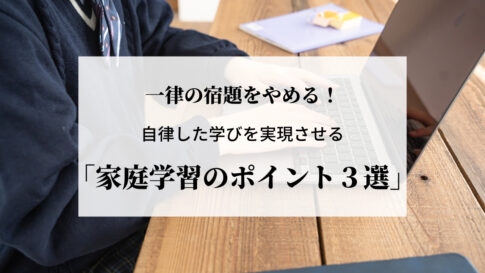









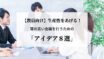
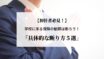
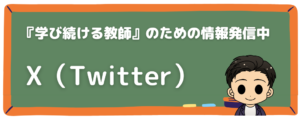
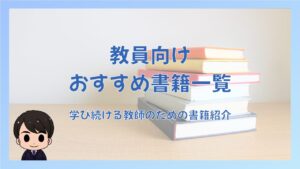
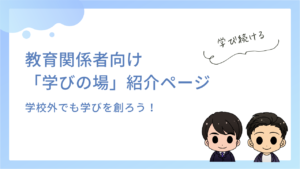
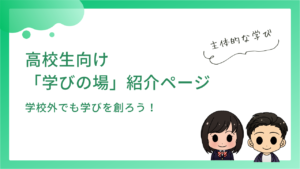
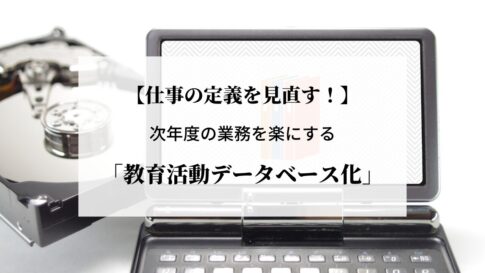
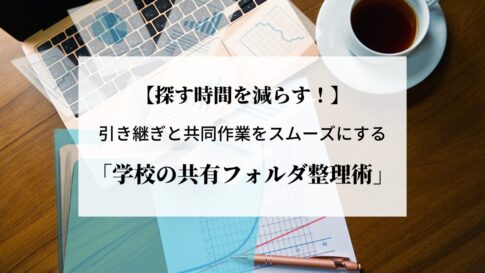
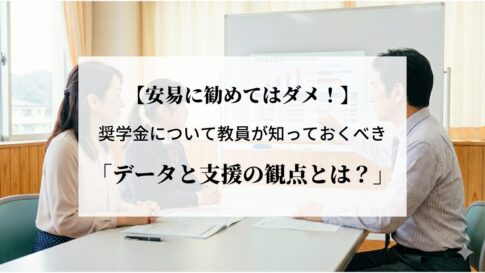
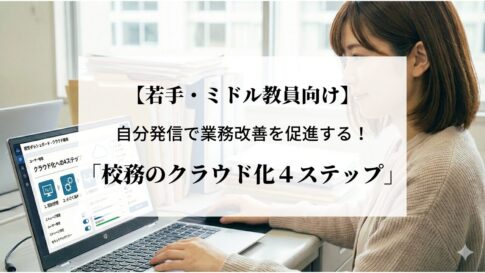
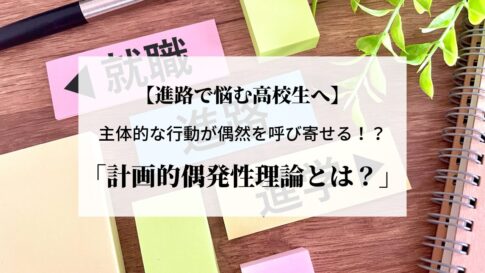
教員になってから「中教審」という言葉を知りました!
国の政策は、教員として把握しておくべきですよね?