夢を語る前に押さえておく!マズローの欲求5段階説【学校現場での工夫例20選】
教員採用試験で一度は覚えた「マズローの欲求5段階説」。しかし、現場に出てから意識して使えている先生はどれほどいるでしょうか?本記事では、各段階の解説に加えて、生徒の現状を見立てるための具体的な実践例を紹介しています。初任者や実習生はもちろん、あらためて生徒理解を深めたい先生方にもおすすめです。
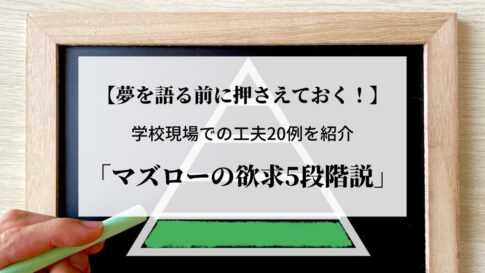 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方教員採用試験で一度は覚えた「マズローの欲求5段階説」。しかし、現場に出てから意識して使えている先生はどれほどいるでしょうか?本記事では、各段階の解説に加えて、生徒の現状を見立てるための具体的な実践例を紹介しています。初任者や実習生はもちろん、あらためて生徒理解を深めたい先生方にもおすすめです。
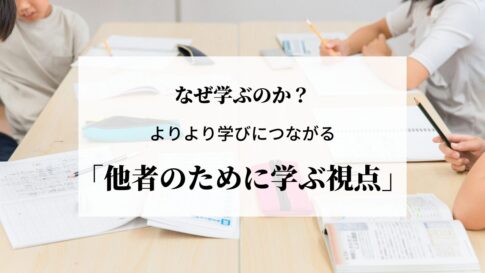 高校生の方
高校生の方「なぜ学ぶのか?」シリーズ第6弾。今回は「他者のために学ぶ」視点から、授業内の学びの特徴について紹介します。自分のために勉強をするだけでなく、みんなのために勉強をする。一見不思議ですが、学ぶ理由の一つとして、大変面白い視点になると思います。これまでの視点をアップデートし、さらに学びを深めてみてはいかがでしょうか。
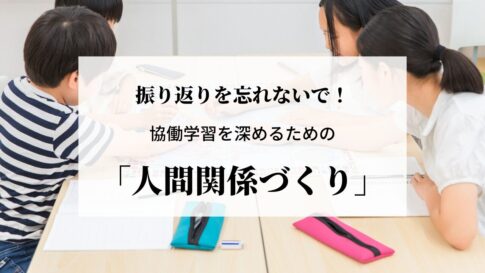 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方協働学習のために取り入れるグループ活動。でも実際に行うと、おしゃべりで終わったり対話が深まらなかったりすることも。これは、グループ学習の取り組み方が分からない、そもそも人間関係ができていない場合があるのです。今回の記事では、協働学習を効果的に進めるための人間関係づくりワークと教科学習に活かす振り返りについて紹介します。
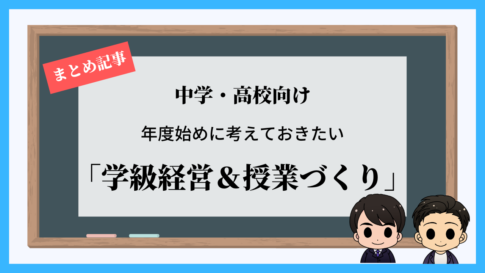 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方新年度は、教員も生徒も新たな気持ちで学校生活をスタートさせます。そのような年度始めに取り組む実践は、教育活動を上手く進めるためのカギとなります。今回は、年度始めに確認しておきたい『学級経営&授業づくり』について紹介します。 一つ一つの内容について、詳細記事もあわせて紹介していますので、ぜひご覧ください!
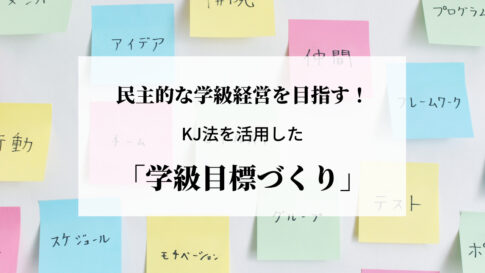 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方生徒が主体的・協働的に学びに向かうためには、クラスの一人一人が学級づくりに関わることが大切です。今回の記事では、KJ法を活用した「一人一人の意見が反映される民主的な学級目標づくり」を紹介します。自分の意見を率直に述べ、その意見が反映された学級づくりが実現することで、所属意識や安心・安全な環境づくりにつながります。