夢を語る前に押さえておく!マズローの欲求5段階説【学校現場での工夫例20選】
教員採用試験で一度は覚えた「マズローの欲求5段階説」。しかし、現場に出てから意識して使えている先生はどれほどいるでしょうか?本記事では、各段階の解説に加えて、生徒の現状を見立てるための具体的な実践例を紹介しています。初任者や実習生はもちろん、あらためて生徒理解を深めたい先生方にもおすすめです。
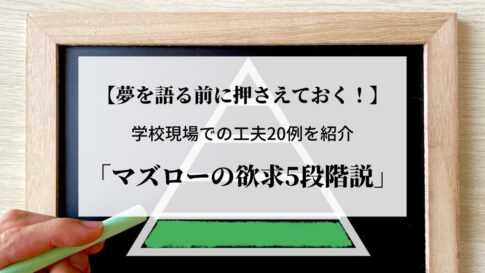 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方教員採用試験で一度は覚えた「マズローの欲求5段階説」。しかし、現場に出てから意識して使えている先生はどれほどいるでしょうか?本記事では、各段階の解説に加えて、生徒の現状を見立てるための具体的な実践例を紹介しています。初任者や実習生はもちろん、あらためて生徒理解を深めたい先生方にもおすすめです。
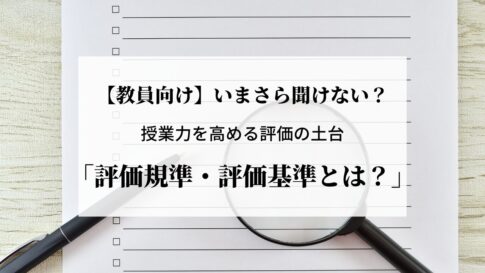 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方「評価規準」と「評価基準」。指導案などで指摘されたことがある先生も多いと思います。教員として大切な仕事の一つである評価。適切な評価は生徒の成長を促します。また評価をしっかり考えることは、授業をよりよくすることにもつながります。今回は、評価の土台である2つの「きじゅん」について、分かりやすく解説していきます。
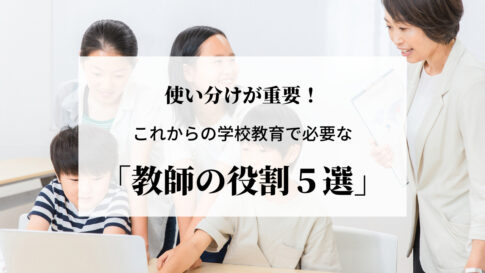 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方これからの時代に必要な教育を実現するためには、従来のような一斉授業に頼った知識の伝達や一方的な生徒指導・進路指導では通用しません。教師は教えるだけでなく、それぞれの教育場面に応じた役割を担っていく必要があります。今回は、これからの時代に求められる教師の役割について5つ紹介をしていきます。
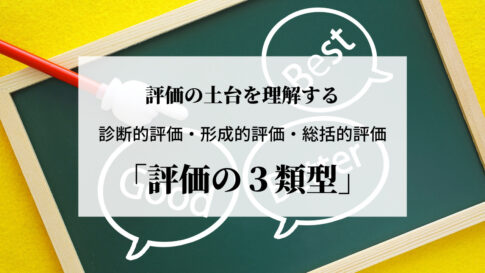 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方診断的評価・形成的評価・総括的評価とはアメリカの教育心理学者ブルームによって分類された評価の3類型です。多くの教師が「評価=評定=総括的評価」となっており、学力テストに依存した評価を行っています。生徒の学力を向上させるためには、評価の土台である3つの評価を理解して、「指導と評価の一体化」を目指す必要があるのです。