【教員向け】手順をいちから解説。YouTubeで動画教材を配信しよう!【メリット紹介あり】
自身で作成した動画を配信する際に「生徒にとって見やすいプラットフォームか」「動画管理が煩雑にならないか」など、視聴者(生徒)と配信者(教員)の手間をできるだけ取り除くことが大切です。この課題を簡単に解消してくれるのがYouTube配信です。今回は、初めてYouTube配信を行う先生に向けて、一から手順を紹介をします。
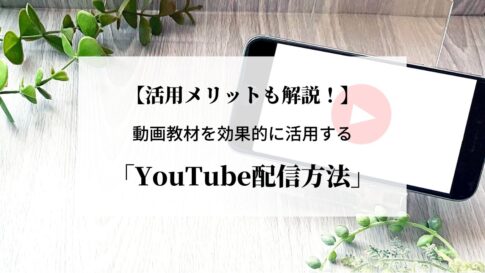 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方自身で作成した動画を配信する際に「生徒にとって見やすいプラットフォームか」「動画管理が煩雑にならないか」など、視聴者(生徒)と配信者(教員)の手間をできるだけ取り除くことが大切です。この課題を簡単に解消してくれるのがYouTube配信です。今回は、初めてYouTube配信を行う先生に向けて、一から手順を紹介をします。
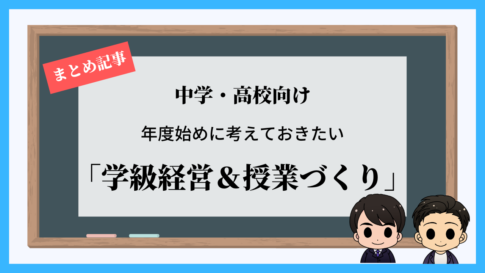 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方新年度は、教員も生徒も新たな気持ちで学校生活をスタートさせます。そのような年度始めに取り組む実践は、教育活動を上手く進めるためのカギとなります。今回は、年度始めに確認しておきたい『学級経営&授業づくり』について紹介します。 一つ一つの内容について、詳細記事もあわせて紹介していますので、ぜひご覧ください!
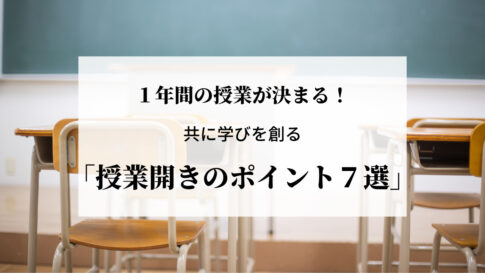 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方最初の授業でしっかり授業開きをすることは、1年間学習を進める上で重要な役割を果たします。授業は生徒と教師でともに学びを創る場ですから、授業開きによる方向性の共有は大切です。今回の記事では、授業開きで何を伝えるか、自身の経験から紹介していきます。「1年間の授業をよりよくしたい」という方はぜひ読んでみてください。
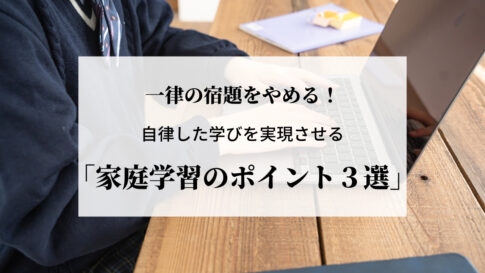 教員・教職志望の方
教員・教職志望の方大量の宿題を一律に課して、問題をたくさん解く経験を積ませる学習方法。これは教員側が「これだけやってほしい」という教師主体の学習なのです。一人ひとり個性がある生徒相手に、一律の宿題でよいのかと考えると疑問です。今回は一律の宿題を廃止し、生徒が主体的に家庭学習を進めるための方法を紹介します。